街々書林 Books & Gallery
2023年6月、吉祥寺の中道通りにオープンした書店。「旅する本屋」を掲げ、旅に関する本や雑誌、雑貨を販売。店内奥には貸ギャラリーも。
-
- 営業時間
-
12:34~18:00
- 定休日
-
月、火曜、年末年始(臨時営業、臨時休業あり)
-
- 住所
-
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町3-3−9
-
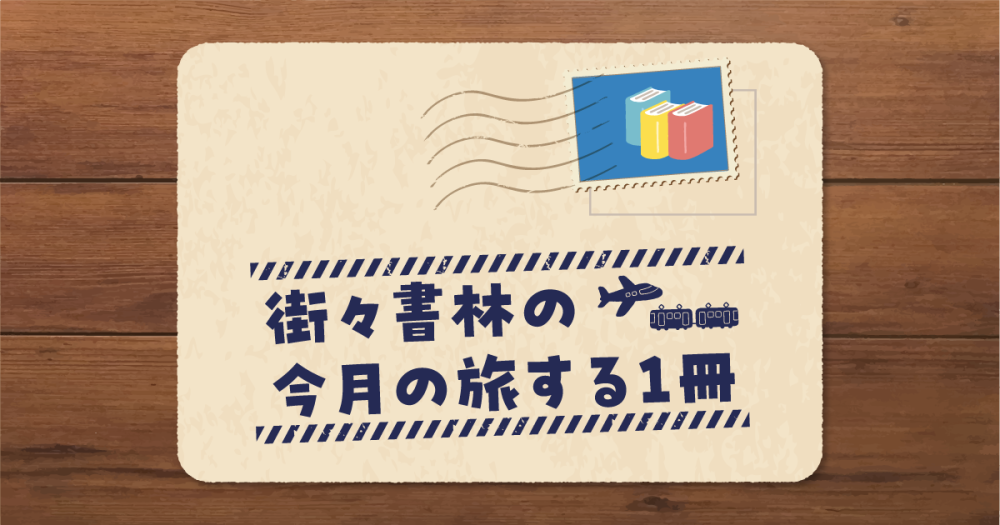
吉祥寺中道通りに位置する「街々書林 Books & Gallery」の店主であり、旅に関する本を執筆してきた「旅行作家」でもある、小柳淳さんによる月イチの連載コラムです。本の世界の「旅」を、どうぞお楽しみください。
「週刊きちじょうじ」と「週刊きちじょうじオンライン」で毎月第1週にお届けしている「街々書林の今月の旅する1冊」。 吉祥寺中道通りにある「街々書林 Books & Gallery」は、旅にまつわる本や雑誌、雑貨を販売しているユニークな書店です。
このコラムは、街々書林の店主であり旅に関する本を執筆してきた「旅行作家」でもある、小柳淳さんによる月イチの連載コラムです。本の世界の「旅」をどうぞお楽しみください。
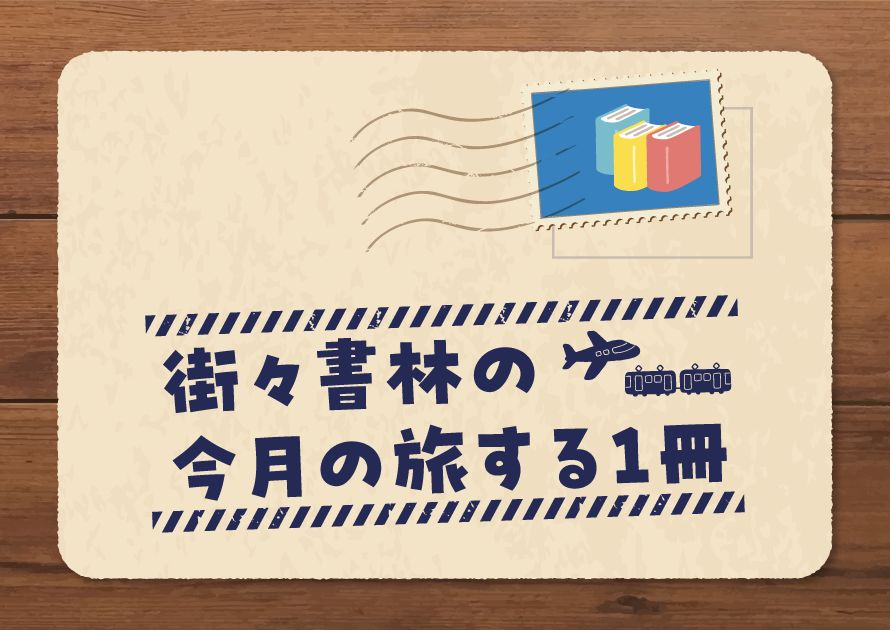
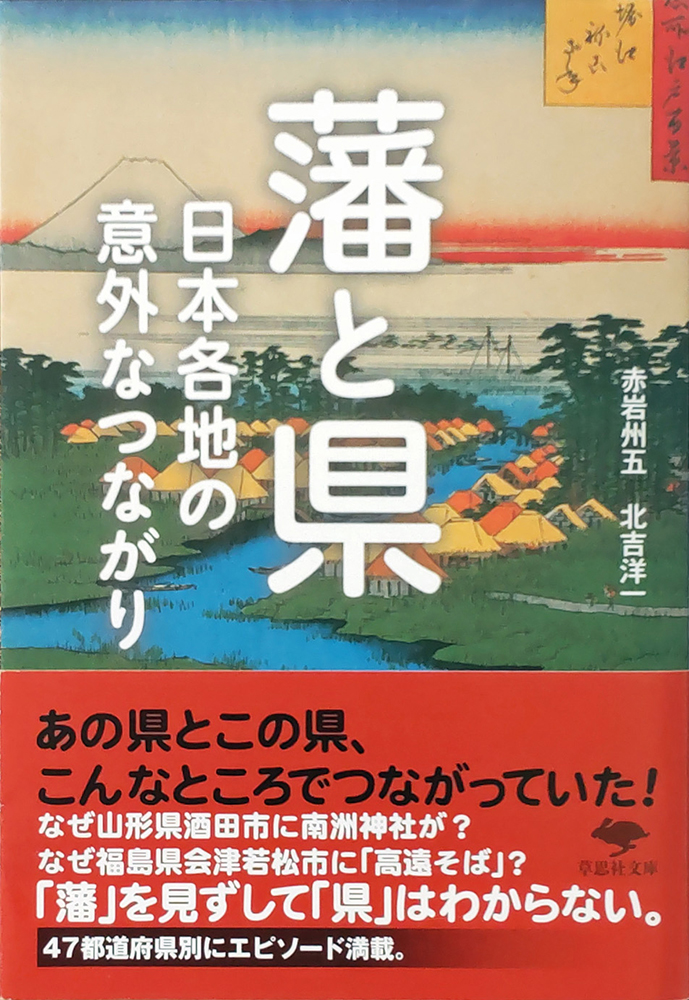
藩と県 日本各地の意外なつながり
赤岩州五 /北吉洋一 著
草思社
価格:880円
発売日:2019年2月8日
ページ数:272ページ
書籍詳細
日本各地のお国柄や文化は県という単位よりも、かつての藩の区分によるところが大きい。都道府県は明治維新後の設定だから歴史は100年ちょっと。それに対し、藩は江戸時代に始まり400年以上前からだ。藩は270くらいあったという。だから藩のまとまりごとのお国柄がけっこう存在するのだ。

ある藩では米価下落時に買い支えるなど領民を保護したケースもあり、藩や為政者により暮らしに違いがあった。大名が転封というお国替えになると、元の領地の農産物や工芸、医薬の技術が新領地に一緒に移転するということもあった。かと思うと、参勤交代により定期的に江戸に住む大名や武士も多く、江戸での他藩・他地域との交流から技術や学術が移転したケースもあるという。幕府は戦略的要地に親藩・譜代大名を置き外様大名をけん制するなど、配置にも気をつかっていたようだ。たとえば、九州北端の小倉藩には譜代の小笠原家が江戸初期に転封となり、九州の外様大名の監視をしたというのだ。幕末から維新期は内戦に近い状況もあったため、藩が幕府方か新政府かどちら側に立ったかで、他地域との屈折した恩讐の感情がその後に残りもする。また、東北の庄内藩は幕末に徳川方で戦ったが、敗戦後官軍の西郷隆盛の温情で処分は比較的軽く、庄内と薩摩相互の交流につながったということもあった。

この本は代表的な藩を取り上げて、大名家の変遷、維新期の立ち位置、江戸屋敷などを説明する。現代に続く工芸品の始まりのエピソードや領主の大名家の変遷なども添えられ、多数の藩の特徴が浮びあがってくる。旅先で名産品や美味しいものに接したとき、かつての藩ごとの工夫や特徴が現代に花開いていることを感じるのもいい。
2023年6月、吉祥寺の中道通りにオープンした書店。「旅する本屋」を掲げ、旅に関する本や雑誌、雑貨を販売。店内奥には貸ギャラリーも。
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町3-3−9


